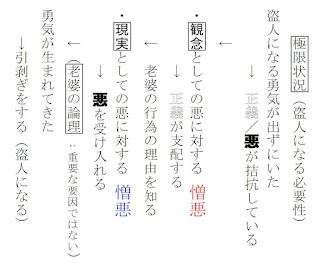さて「木を見る…」と、教科書のいう「関連教材」、「少女たちの『ひろしま』」をどのように読み比べるか?
まず、両者の主旨を、共通する一文で表現してみよう。関連しているとは、共通部分があるということだ。
視点を変えると物事は違って見える。
だいたいこんな言い方になるはずだ。これをスキーマとゲシュタルトという語を使って言うと?
スキーマが変わると違ったゲシュタルトになる。
「スキーマ」と「ゲシュタルト」という言葉がどんな概念なのか、だんだんつかめてきたろうか。
「スキーマ」とは言ってみれば「見方」のことで、「ゲシュタルト」は「見え方」だ。見方を変えると見え方は変わるのだ。
さて、そうした言い方では、両者は共通しているが、では、それぞれの文章は、具体的にはどのように見方を変えると、どのように見え方が変わると言っているのか? 両者に相違はあるんだろうか?
対応している要素を比べてみよう。
だが何を比べるのか? 何と何の「対応」を比較するのか?
こういう時には例によって対比を捉える。
ただし今回の対比は「対立」ではなく「並列」だ。
対比の多くは「対立」だ。「AではなくB」というとき、「A/B」は対立構造にある。Bのことを言いたいときに、Aを対立項として比較することでBの輪郭が明確になる(こうした対立構造もスキーマのひとつ)。
一方、複数の項目をそれぞれ対等に扱うのが「並列」や「類比」だ(「並列」と「類比」の違いはまたいずれ)。
今回の「視点を変える」では、どのような「視点」なのかを対比的に捉えよう。
「木を見る…」では「視点」の「角度」と「倍率」を変える、と述べられている。対比としては「角度」についての言及は少ないので割愛して「倍率」の方のみ書き出してみる。
全体/一部
遠くから/近づいて
ひいて/寄って
といったところか。
一方、見え方がどう変わるかといえば、「全体」を見るときには「まとまり」として見るのだと言っているが、それに対比される「一部」を見るとにどう見えているかは詳述されていない。「葉っぱの一枚一枚」「瞬間ごとに移りゆく模様」「光と影のゆらめき」といったイメージは提出されているが、それを抽象化した言葉が見つからない。むしろ「アリの目に世界はどう見えているか」と、疑問を呈して終わっている。
さて問題は「少女たちの『ひろしま』」の方だ。ここではどのような「視点」が対比されているか?
これは簡単にはいかないはずだ。一単語の対比で済むわけではないし、文中から容易く抜き出せるものでもない。いろんなレベルの表現を重ねることで、しだいにその視点の違いが捉えられる。
対比が「視点(スキーマ)を変える」と「見え方(ゲシュタルト)が変わる」のどちらなのかを考えながら挙げてみよう。
例えば
暗い/明るい
という対比が挙がるが、これはそのように視点を変えたというより、ある視点から見たときの印象の違いを表している。
ではどのような視点の違いがここでは対比されているか?
対比を挙げる時は、概念レベルを揃えよう。例えば名詞、動詞、形容詞などと品詞を揃えるとか。なるべく。
一人三つ以上、班で5~6個、などと言ってみると、クラス全体では十数個の対比的な表現が挙がってくる。そのようにいくつもの言葉を重ねることで、視点の違いによる見え方の違いが捉えられてくる。
歴史/生活
戦争/日常
悲惨/美しい
史料/日用品
これをひとつなぎにしてみると、「歴史」といった大きく物事を捉えようとすると、その服は「戦争」の「悲惨」な爪痕を示す「史料」と見えるが、一「生活」者の視点から見ればそれは戦時下を生きる少女たちの「日常」を想起させる「日用品」として「美しい」ものに見える…。
実は挙げてみると、思いのほか「見方」と「見え方」の区別は明確ではない。「戦争」は「見方」か「見え方」か。どちらともいえる。「歴史」とか「政治」とかいうスキーマで見たときにそれが「戦争」というゲシュタルトを現すのだと言ってもいいし、「戦争」というスキーマから見たときに、服が「悲惨な過去」を示す「史料」として見えると言ってもいい。
クラスによっては面白い対比が提起されたりもした。
作家/一女性
という対比は、まさしく視点の違いを指摘している。これは筆者・梯さんの中の視点の対比だが、これを
梯さん/石内さん(写真家)
という対比で表現した人もいた。なるほど。梯さんには服が「悲惨な戦争の史料」に見えているが、写真を撮った石内さんは「若い娘の密かなおしゃれ」として見ている。その時、その服の主は、
被爆者/一少女
としてその姿を現す。